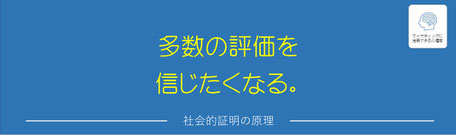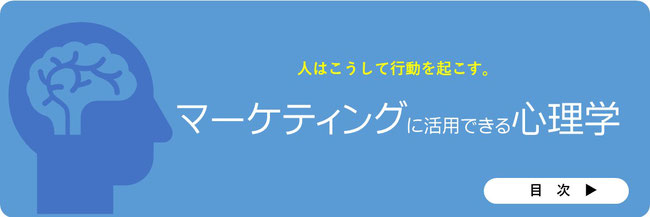ウィンザー効果
”当事者からよりも第三者からの意見を信用する”心理効果がウィンザー効果です。
マーケティングでは、商品レビューに多く利用されていますが、商品の販売元よりも第三者の意見を聞きたい消費者が多いということは、誰もが理解していることでしょう。
マーケティングの視点で重要となるのは、「誰の意見なのか」という点です。
インフルエンサーと呼ばれる”情報を拡散する存在”が注目されるようになった今の時代に、ウィンザー効果は改めて重要な心理効果であり、”第三者”を的確に選定することで結果は大きく変わります。
ここでは、ウインザー効果をマーケティングに活用する際に知っておくべき基本事項と、注意点などを考察します。
ウィンザー効果の基本

多くの人は、その情報で利益を得る人や何か目的を持っている人が発信する内容には、嘘や誇張があるものだと考えます。
例えば、商品を売るために発信されている情報は、良いことを強調していると捉えるでしょう。
そこで、メーカーの宣伝文よりも、身近な友人が使った感想など、「その情報に利害関係が無い人」が言っていることの方が本当のことだと感じるのです。
ウィンザー効果の名称の由来は、小説のセリフ
ウィンザー効果の名称の由来は、アーリーン・ロマネスの小説『伯爵夫人はスパイ』の中に出てくるセリフです。
登場人物のウィンザー伯爵夫人が「第三者の褒め言葉がどんな時も一番効果があるのよ、忘れないでね」と言ったことから、”ウインザー”の名が取られています。
ウィンザー効果をマーケティングに活用するには
ウインザー効果は、商品やサービスの訴求について多く活用されています。
商品の購入を検討する時、その商品の優れた点とそれが本当なのかどうかは、誰もが知りたいことでしょう。
そんな時、販売主が発信する広告や販促ツールよりも、第三者の立場にあたるメディアやインフルエンサーが発信する情報のほうが信頼される傾向にあります。
合わせて、その「第三者が誰であるか」がとても重要です。
誰もが様々な情報を手に入れられるようになった現代では、情報そのものの優劣や信憑性は判定しにくく、人は「誰」が発信した情報であるかによってその情報の確かさを判断するようになっています。
いわゆる「何を言うかよりも誰が言うか」です。
情報を発信する第三者が、”よくわからない人”、”信用できない人”、”自分が嫌いな人”だと、ウィンザー効果はあまり発揮されません。
「この人が言うことなら信用できる」「この人には利害関係がない」と思われる人(機関、メディア)が発信することで、ウインザー効果は最大の効果を発揮します。
ウィンザー効果を活用したマーケティング施策例
ウインザー効果が利用されているマーケティング施策には以下のようなものがあります。
1)ユーザーレビュー
その商品を購入した人のレビューをサイトやPOPなどに掲載する方法です。
いまやネットショップなどのレビュー機能は基本機能であり、消費者は、実物を利用した人の意見として「広告とは違った情報が得られる」と期待します。
ただし、レビュー特典やアフィリエイトなど、レビュー者にインセンティブがあることが消費者に強く伝わると、そのレビューコメントの信頼性は低下します。
2)パブリシティ活動(プレスリリース)
雑誌やTVなどマスメディアに取り上げてもらうために、ニュースソースとして情報を発信する方法です。マーケティング界ではパブリシティ活動と呼ばれ、昔からある最も基本的な手法です。
ここでは、「メディアが自主的に掲載・報道する情報=企業が依頼する広告ではない」という前提があり、マスメディアが”信頼できる第三者”の役割を担っています。
しかし、メディアに公正がない(忖度がある)と感じられると信用は低下します。
3)ペイドパブ(編集タイアップ)
雑誌などが「純広告」ではなく、「有料記事」として発信する手法です。記事は雑誌側が制作するこことのテイストが加味され、雑誌の読者から支持されやすくなります。
しかし前述のパブリシティ(無料)と違って、「ペイドパブ(PR広告)」と呼ばれ、「広告メディア料+製作費」としてかなり高額料金が発生し、利益関係がないとは言えません。この点では、実質広告扱いなので、厳密にはウィンザー効果とは言えないかもしれません。しかし、記事の中で、専門家の評価や利用者の客観的な感想などを示すこともでき、演出としては、ウィンザー効果を狙ったものになっていることが多いです。
なお現在は、ペイドパブ記事には「広告」の表示をし、読者側が「企業の依頼記事である」ことがわからなけらればならないルールになっています。
4)口コミサイトへの掲載
「食べログ」や「@コスメ」のような、特定ジャンルのレビューを集めたサイトに自社の情報を掲載する手法です。
多くの第三者からのレビューが集められることで、自社への評価が同業他社と比べられ、単独で広告宣伝を行うよりも効果的である場合があります。
また、レビュー数が多くなると、バンドワゴン効果で評価が底上げされることもあります。
5)SNSによる情報発信
SNSから情報を収集する人には、「自分がフォローしているインフルエンサーや知人の情報を信じたい」というウィンザー効果が働きます。
そこで企業(マーケティング主)側が、ツイッターやインスタグラムなどのSNSで自然に取り上げられることを狙います。
具体的には
・インフルエンサーへの商品提供
・SNSユーザーのネタになりそうな話題づくり
などがあります。
ウィンザー効果を利用する時の注意点
現代社会では、商品レビューを含め「商品の販売に関する第三者が関与する」マーケティングには、そのほとんどに多かれ少なかれ「利益」が存在しています。
そして、多くの消費者がそれを認識しているので、一般市場でのマーケティング施策のシーンで、純粋なウインザー効果を期待するのは難しくなっているかもしれません。
そして、これまでも「広告・宣伝」の世界では、”売り込み”の手法に抵抗を感じる消費者が一定数いるため、"広告色”を消す手法は長年工夫されてきました。
広告らしくない広告を狙う展開も多くありました。
その後、広告であることを隔そうとする手法はNGとなり、現在では記事広告などは「広告であること」を明記するルールが生まれ、広告であることがきちんとわかる体裁であることが大切になっています。
特に昨今は、”ヤラセ”や”ステマ(ステルスマーケティング)”の問題が話題になることが多く、利益供与を隠すような行動をすれば、低評価に繋がったり、炎上となることがあります。
このようなことからウインザー効果を狙う場合は、意図的な施策として実行するよりも、自然発生した口コミや自発的な著名人の推薦などを想定することが賢明でしょう。
インフルエンサーの利益について
ユーチューバーが代表的ですが、近年はインフルエンサーが「広告収入を得る」ことは広く知られています。
そして、上記のように、第三者であっても、利益のための情報発信として拒否反応を見せる人も一定数います。
しかし近年では、例えばインフルエンサーが商品紹介で利益を得ていても、コンテンツの内容や企画テーマなどよって、商品の高評価、関心アップに繋がることもあります。