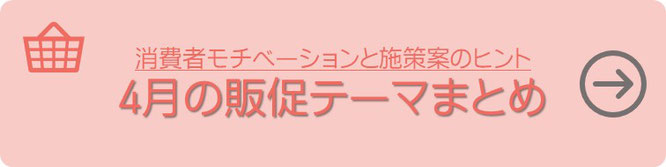春に旬を迎える食材
山菜(タラの芽、ウド、ふき、わらびなど)
山菜とは山などに自生している食べられる野草のことで、アクの強さや独特の苦みが特徴で新芽や若い茎などを食用とする。多くは3月下旬~6月上旬に旬を迎える。春の訪れを告げる山菜として知られる「ふきのとう」、わらびやタラの芽、ウドなど。
菜の花/菜花(ナバナ)
菜の花は初春になると黄色い花が咲き始め、食用となるのは花が咲く前のつぼみと花茎を収穫したものなので、花の開花の前の時期(1月~3月)が旬にあたる。
アスパラガス
アスパラガスは産地によって収穫時期が異なり、本州産は4~5月頃、北海道産は6月頃に旬を迎える。アスパラガスは地中海原産のユリ科の植物で、地表から伸びてきた新芽の茎を切り取ったものが食用になる。
春キャベツ
3~5月頃に旬を迎える春キャベツは、「春玉」や「新キャベツ」とも呼ばれ、実は通年売られているキャベツ(寒玉)とは異なる品種。春キャベツは鮮やかな黄緑色で形が丸く、葉の巻きがゆるい。柔らかくてみずみずしい葉はサラダなどの生食に適している。
新玉ねぎ
新玉ねぎは、収穫後すぐに出荷される早採り玉ねぎの総称。旬は3~5月頃。皮が薄く、みずみずしい質感、辛みが少ないのが特徴。通常の玉ねぎは春に収穫し1ヶ月ほど乾燥させてから出荷するが、新玉ねぎは収穫後すぐに出荷される。
たけのこ
たけのこは2月下旬から初物が出回りはじめ、3~4月頃に旬を迎える。たけのことは春になって出てきた竹の若芽を食用にしているもので、竹の成長スピードが非常に早いことから、収穫時期は限られている。
鰆(さわら)
「鰆(さわら)」の旬は地域によって異なり、関東では12~2月頃、関西では3~5月頃。回遊魚である鰆は、餌を求めて春~夏にかけて北上し、秋~冬にかけて南下する。5~6月にかけては産卵のため瀬戸内海付近の海域に集まるため、さわらの産地として有名で、関西では鰆は春の魚として認識されている。
しらす
しらすとはイワシの稚魚の総称で、一般的には3月下旬~5月頃が旬とされてる
環境資源保護のため、しらす漁には県ごとに禁漁期間が設けられており、産地として有名な静岡県や神奈川県では、3月下旬以降に漁が解禁するので、春先にしらすの初物が出回る。
鰹(かつお)
鰹は年に2回旬があり、3~5月頃に獲れるものは「初鰹」、9月頃に獲れるものは「戻り鰹」と呼ばれる。鰹は、2~3月頃に鹿児島県沖から回遊をスタートして北上し、8月~11月頃にかけ再び鹿児島県沖を目指して南下する。そのため春鰹は、まだ十分な脂を蓄えておらず身が引き締まった赤身が特徴。さっぱりとした味で「鰹のたたき」に適しており高知県の名産としても有名。
鯛(たい)
一年を通して漁獲量のある魚だが、春と秋の年に2回旬を迎えるとされる。3~5月頃が旬の春の鯛は「桜鯛」と呼ばれ、産卵のために浅瀬へとやってきたもの。産卵を控えた鯛は脂がのっていて、卵や白子を楽しめる。「桜鯛」の名前の由来は諸説あるが、春の雌の体全体が桜色をしており、雄には桜の花びらのような白い斑点が見えるから、というのが一説。
いちご
現在はハウス栽培が主流で、クリスマスケーキの材料としての需要も高いことから、12月頃から収穫されるが、自然栽培での旬は4~6月頃。