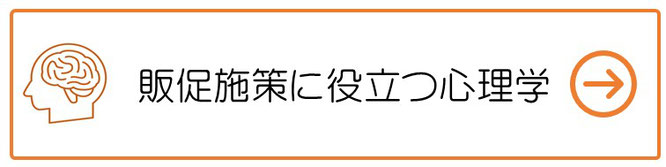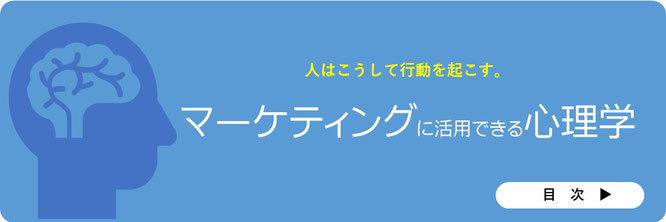決定回避の法則
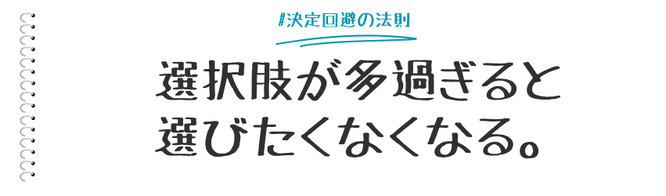
決定回避(選択回避)の法則とは
選択肢が多過ぎると、選択を放棄してしまう心理が決定回避の法則である。
人にとってたくさんの情報の中からより良いものを選びだすことは、贅沢で楽しいという面もある一方で、物事を選択するための脳のエネルギー消費を控えようとする本能から、多くの情報を検討するのを避けるのだと言われている。
決定回避の法則の実証実験(ジャムの実験)
社会心理学者シーナ・アイエンガーの論文で紹介された「ジャムの実験」がある。
この実験では、24種類のジャムと6種類のジャムを日を分けて売ったところ、6種類のジャムの方が購買率が高かったという結果が出ている。
選択肢が少ない方が選ばれやすくよく売れるという結果であり、典型的な販促施策例の一つと言える。
決定回避の法則をマーケティングに活用するには
たくさんの選択肢は、興味を抱いてもらう効果はあるが、選ぶことに負担を感じる人にとっては、「多すぎてどれがいいのかわからない」という気持ちから「選べないから買うのやめた」という状況となってしまう。
特にその商品についてあまり詳しくない人や、自分の判断に自信のない人などには、特に強く決定回避の法則が働く。
選択肢を絞って、選びやすく。
多すぎる情報や選択肢は、選ぶことに”負担”が生じる。
その負担を軽減するべく、選びやすい状況をつくる、つまり選択肢を絞ることが有効である。
また、負担のない適度な数の選択肢は、それらの情報に集中してもらう効果もあるので、情報を相手にしっかりと理解してもらうことにも繋がる。
決定回避の法則に有効な選択肢の数
決定回避させないためには選択肢を絞ることが有効な手段だが、一般的にすべて商品が1つだけの選択肢という訳にもいかない。
実際には、選択肢の数はどのくらいが適切なのか。
人が疲れない選択肢の上限が、マジカルナンバー
選択肢に有効な数としてよく語られるのが、マジカルナンバーである。
マジカルナンバーとは、人が一度に処理できる情報の限界を数値化したもので、長年その数は7±2とされてきたが、2001年に心理学者ネルソン・コーワン氏が提唱した新マジカルナンバーは、4±1となっている。
情報化社会となり、全体の情報量が多くなってくると、人はますます情報処理を簡略化したくなることから、情報が溢れる現代では、より完結にまとめられたものがこの好まれるようになるだろう。
3択なら選びやすい
人はレベルに差のある3つの選択肢の場合、真ん中を選ぶことが多い、という松竹梅の法則がある。
3つの選択肢は負担のない数であり、またその3つに3段階の差をつけることで、選びやすさも増す。
松竹梅の法則も決定回避の対策にも貢献できる心理法則の一つである。
決定回避の法則を活用したマーケティング手法の例
決定回避の法則が活用されている具体的なマーケティング施策の例として以下のようなものがある。
「おすすめ」の紹介
ショップや飲食店では、「当店のおすすめ」を紹介することで選択肢を限定させる。
インターネットショップやインターネット広告では、「リコメンド機能(推薦機能)」を使って、「お客様の興味関心がありそうな商品の種類の絞込み」を行っている。
ランキングの発表
リストアップ表記
「これだけでOK!失敗しない△△7選」などの表記で、厳選した限定的な選択肢として訴求する。
TVや雑誌の特集、ネットの記事などでよく使われている手法である。
3つの選択肢を用意(松竹梅戦略・ゴルティロックス効果)
松・竹・梅など、選択肢を3つのレベルに分けることで、真ん中の選択肢が選ばれやすくなることを狙った手法。特に、3という少ない選択肢は、近年のマジックナンバーの理論にも当てはまっている。
カテゴリー分け
実際に提供している情報数や商品がもともと多数はある場合は、3~7つ程度のカテゴリーに分けて見せることが効果的。
継続のために、あえて選択肢を増やす
定期購入や会員システムなど継続性のある商品の場合、一度購入を決めた人はそれ以外の選択肢が多いと、変更することや別のものを選ぶことに負担を感じ、継続が続くことがある。
特に気に入ったものが見つかった人は、「現状維持の法則」「保有効果」「損失回避の法則」などのそれを変えたくないという心理効果も合わせて働く。
例)
・携帯電話の契約コース