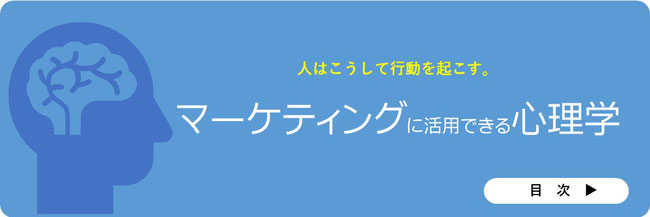新近効果
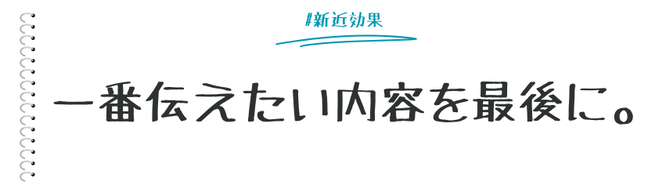
新近効果とは
新近効果とは、「最後に与えられた情報でその印象が決定されやすい」という心理効果のこよ。
『結局のところ、〇〇なんだ』と考えるような心理であり、マーケティングでは、セールストークやコピーライティング、WEBコンテンツなどに幅広く活用されている。
※一方で、全く逆の展開で作用する「初頭効果(最初に接したものが印象に残る)」という心理効果がある。
新近効果をマーケティングに活用するには
一番伝えたい内容を最後に表現しその印象を強めるという効果から、説明コピーやCM動画などストーリー的な表現をできるもので使うことが多い。
しかし、最後まで情報に接してもらわなければならないため、ある程度の関心や時間の余裕をもっているターゲットとのコンタクトに適している。
※類似する心理効果「ピーク・エンドの法則」
新近効果と関連する心理効果として「ピークエンドの法則」がある。
ピーク・エンドの法則とは、「人が記憶の多くは、時間的な長さではなく、クライマックスに当たる場面と、終わりの場面の2つの印象で作られている」という理論。
例えば、映画では、ストーリーが一番盛り上がったシーンとラストのシーンの2つが印象に残り、ラストシーンの終わり方によってどのような映画であったか記憶されることが多い。ストーリーがある演出のコンテンツの場合は、エンディングに加えて、“盛り上がりのポイント”を作ることが重要とされる。
新近効果を活用したマーケティング施策の例
親近効果が活用されている具体的な施策例は以下のようなものがある。
Webサイトのランキング記事
複数の商品やサービスを紹介し、一番売りたい商品やサービスを記事の終盤で紹介する手法として、ランキング形式での紹介がある。
商品を順番に紹介していき、1位に売りたい商品やサービスを提示する。
口コミの紹介(掲載)順
口コミやレビューはポジティブ評価とネガティブ評価がありますが、新近効果を意識すると、掲載順はポジティブ評価を後の方にした方が効果的です。(※初頭効果を意識すると逆になります。)
実証実験の一つの例としては、慶応義塾大学大学院で行われた実験で、Webページの最初にネガティブな口コミを掲載し、最後にポジティブな口コミを掲載して被験者にWebページを通読してもらった結果、被験者は口コミされた商品やサービスに対してポジティブな印象を持ったというものがあります。
販促コピー(セールスコピー、セールストーク)
販促用のコピーやセールストークにおいて、売りたい商品のメリットや強みを後に訴求します。商品やサービスの特徴をデメリット→メリットの順番で紹介し、メリットの方を強く印象に残す手法です。
【例】
・ちょっと高いが、かなり美味しい(Dole厳選バナナ)
ドラマ仕立てのCM
ストーリーのあるドラマなどで最後の結末で商品やブランドを印象づけます。インパクトのあるラストシーン、ユーモアやオチがあるストーリーなどが効果的です。