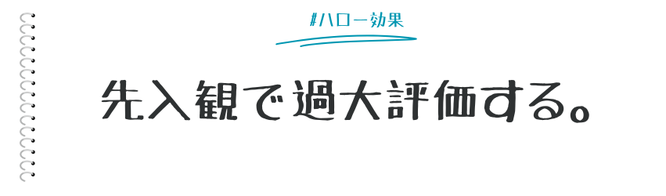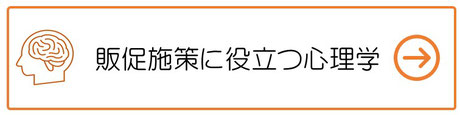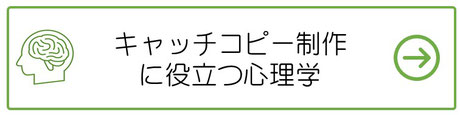ハロー効果
ハロー効果とは
ハロー効果とは「物事の評価が、一部の優れた特徴や権威に影響されしまう」心理効果。
例)
・「高学歴」の人は「真面目でしっかりした」人格者だろう
・「高級ブランド」の商品を「素材が良く、デザインも優れている」ものだろう
特に、ある秀でた特徴を全体評価として捉えることをポジティブハロー効果といい、主に過大評価という意味で使われている。
※「ハロー」は、HelloではなくHalo(後光、光輝)のこと。
ハロー効果の実証
アメリカ教育心理学の創始者とも言われるエドワード・L・ソーンダイクが、1929年に発表した論文で、この心理現象について「ハロー効果」という言葉をはじめて使ったとされる。
ハロー効果をマーケティングに活用するには
ハロー効果がマーケティングに影響する場面には、ポジティブハローとネガティブハローがある。
語源からは、ハロー効果は「ポジティブハロー」と捉えるのが基本だが、マーケティングでは、”逆効果”に対しても「ネガティブハロー」という言葉を使って表現することがある。
ポジティブハロー効果
マーケティング施策に活用される基本的なハロー効果は、商品やサービスが良い印象や高い評価を得られるようにするポジティブハロー効果である。
多くの人が高評価をする要素を前面に打ち出し、その商品やブランドの全体的な評価を高評価へと導く。
ネガティブハロー効果
ネガティブハロー効果とは、社会でマイナスの評価を受けるモノやコトが商品とリンクすると、その商品も悪い特徴に影響されてしまう現象。
SNSでの炎上やイメージキャラクターを務めたタレントの不祥事などが、商品に非はなくても、ブランドや企業のイメージを悪くしてしまう例がある。
近年はこのネガティブハローのリスクヘッジも重視されている。
ハロー効果が活用されるマーケティング施策の例
商品の特徴を前面に押し出す
”優れた特徴”をアピールすることで、商品全体への印象を高める。
(1)ロングセラーである
継続的に高い評価を得ているであろうと想像できる利用実績や歴史をアピール。流行に左右されない堅実な商品であるのだろうという印象を与え、商品の信頼性や安定感を重視するターゲットに有効。
【例】
・創業〇〇年
・皇室御用達 など。
(2)社会的に注目されているテーマ
目立つ特徴の中でも、多くの消費者が気にしていることや社会で話題になっている事について、対応していることをアピール。
社会的に「これが良いことだ」をいう論が広まっているところがポイントで、求めているターゲットがいるという判断のもとに行うことが有効。多数の人が評価しているものを高く評価してしまう「社会的証明の原理」との相乗効果がある。
【例】
・化学調味料無添加
・シリコンフリー
・動物実験を行っていません など
(3)受賞実績
権威のある他者(機関、団体、コミュニティ)からの評価をアピール。
自分の評価よりも他者の評価を優先する「社会的証明の原理」との相乗効果がある。
【例】
・〇〇賞受賞
・ベスト〇〇に選ばれました
権威者やインフルエンサーによる推奨
専門家や有識者、有名人が商品に関する情報を発信する。
近年SNSなどで活躍するインフルエンサーとは、専門家でなくとも一定の分野で影響力を持っている、目立った特徴を持っている人物のこと。彼らのハロー(後光)によって、「あの人が薦めているのだから間違いない」という印象を与え、商品や情報への信用を高めていく。
商品をレビュー、おすすめするコンテンツ、マーケティング施策は、近年多く存在するが、ハロー効果を意識するならば「何を言うかよりも誰が言うか」が重要となる。
【例】
・美しい女優さんが愛用しているコスメだから、美容効果があるのだろう。
・有名な医師が推奨している健康食品だから、安全な商品だろう。
・一流プロスポーツ選手が使っている道具は、性能が高いのだろう。 など
ただし、先述しているように、インフルエンサーやイメージキャラクターの展開は、ネガティブハローを起こすリスクもある。近年ではインフルエンサーマーケティングがよく知られるようになり、いわゆる「ステマ」などマーケティング的な誘導は過剰に嫌悪する人も多く、展開には注意も必要。
関係者の肩書をアピールする
商品の開発者、スタッフ、企業の代表者など、関連する人物の肩書きや実績を積極的に発信。
高度な技術をもつ専門家や、権威があるとされる人や機関が関わっていることで、信頼を高める。
例)
・社長や責任者など社内での地位が高い人が商品紹介に登場する
・サービススタッフのポジションランクを紹介(チーフ〇〇、エグゼクティブ〇〇など)
スタッフの身だしなみ
販売員や営業スタッフの資格や役職を名札や名刺に記載して専門性を強調したり、ユニフォームや身だしなみでプロフェッショナルであることを印象付ける。
「この人の話(セールストーク、商品説明)は、信用できる」という印象づくりに効果的。
また、スタッフの清潔感・安心感のある姿は、心情的なハロー効果が働きやすい顕著な例である。前述の学歴での性格を判断してしまう例のように、「身なりがちゃんとしている人は、仕事もちゃんとしているだろう」と考えるのはよくあること。
また、ユニフォームは、ブランドをしっかりと表現するためにも重要な施策である。