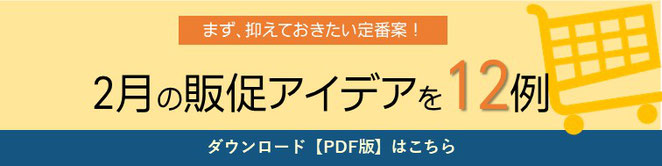バレンタインデーの市場規模はすでに減少へ向かいはじめており、恋愛イベントからの変化、義理チョコ文化への抵抗、高価なハイブランド品への関心低下などの傾向がみられる。
コロナ禍を経て経済活動の回復に合わせて需要の微増はあるものの、職場などでの義理チョコ文化はさらに衰退。
バレンタインの楽しみ方は、「自分が楽しむため」「家族や友人など身近な人と過ごす時間」「日頃の感謝を伝える機会」と捉える人が一段と増えている。
バレンタインデーに関する意識調査
毎年様々な企業やメディアから発表されるバレンタインデーに関する市場調査の結果をシェア。
日本インフォメーションによる調査(2024)
調査地域:日本全国
調査対象:15~59才の女性
サンプルサイズ:900サンプル
調査方法:インターネット調査
調査実施時期: 2024年1月17日~1月18日
・今年プレゼントする予定のチョコの種類は、全体では「家族チョコ」が55%と高い
・今年のバレンタインデーの予算合計は、平均4,008円。昨年と比較すると452円減少
・購入予定場所は「デパート・百貨店」が最も高く36%、次いで「スーパー」が32%
LINEリサーチによる調査(2024)
ぐるなびリサーチ部による調査(2023)
ぐるなび会員の女性ユーザーを対象としたWEBアンケート
調査期間:2023年1月6日(金)~9日(月)
調査対象:全国:20代~60代のぐるなび女性会員1,000名
【サマリー】
・贈る相手は「配偶者」が5割で最多、次いで「自分」と回答した人が3割弱。
・重視点TOP3は「パッケージがおしゃれ、かわいい」「好きなショコラティエ、パティシエ」「限定品」 で昨年と変わらず。4位は昨年の「高級ブランド」に代わり「低価格」がランクイン。
・義理チョコを購入する人は3割。
ハンドメイドマーケップレイス「Creema」による調査
Creema(クリーマ)ユーザーを対象としたインターネット調査
調査期間:2023年1月10〜11日
調査対象:Creemaユーザー 男女1,115名
【サマリー】
・「自分用に購入」がする人が3割。2年連続で増加で1.5倍に。
・目的には、「推し活」と「ペット」がランクイン
・贈る相手は「パートナー」「家族」「自分」がトップ3
「名古屋タカシマヤ」による調査(2022)
同社ホームページにてアンケート
調査期間:2022年12月20日(火)~2023年1月6日(金)
有効回答数:2,455名
【サマリー】
・「義理」は過去最低、贈りたいのは“身近な大切な人“
・自分で楽しむのはもちろん、家族でシェアして楽しむ方も多い
Job総研による調査(2022)
社会人を対象としたインターネット調査
調査対象者:全国 / 男女 / 20~69歳
調査条件:1年以内~10年以上勤務している社会人 20人~1000人以上規模の会社に所属
調査期間:2022年1月28日~2月2日
サンプル数:565
【サマリー】
・女性回答者全体の84.6%が今年職場でバレンタインを実施しない
・2019年からの推移でバレンタインのプレゼントを渡す人は毎年減少
・回答者全体の45.9%が「職場で義理チョコを渡す文化」について反対派
バレンタインデーの市場規模の推移

上図は、visualizing.infoが総務省の「家計調査(チョコレート)」のデータをもとにバレンタインの市場規模を推計したもの(企画の種にてグラフ化)。
二人以上の世帯全体の単身世帯の支出額をもとにしたもので、消費者が実際にチョコレートに使った金額、つまり需要側からみた市場規模である。
2017~2018年でピークアウトしているとされる。
東京都内百貨店・ショッピングセンターのバレンタインフェア
百貨店では今年もバレンタインフェア(イベント催事)が行われるが、会期や規模はここ数年で縮小傾向がみられる。
関心の高い層が注目するブランドなどは予約やネット販売などで購入され早い時期に売り切れになるなど、2月14日当日まで潤沢に販売するわけではないブランドが増えている。
都内のバレンタインフェア公式サイト一覧
2024年のチョコのトレンドは?
バレンタインが恋人イベントでなくなった今、近年の日本の経済状況も鑑みると、高級ブランドチョコレートへの関心は下降気味。
価格やブランド名にこだわらず、自分が関心を持つチョコ―レートを購入する人が増え、選択肢は多くなっている。
また、チョコレートの原材料(カカオ)の産地に目を向けて、オーガニックやフェアトーレードなど“サスティナブル”をテーマとするチョコレートも多くなっている。
バレンタインの歴史
世界でのバレンタイン
「女性が男性にチョコレートを贈る」というバレンタインデー風習は、世界的にみると日本だけ、というのは今ではよく良く知られていることと思います
世界的には、恋人の日、夫婦とカップルの日と捉えられることが多く、プレゼントを贈り合うのはチョコレートに限らず花やカードなど、また女性から男性よりも、男性から女性へ贈ることの方が多いようです。
日本のバレンタインの発祥は?
この日本型のバレンタインは昭和40年代にはイベントとして定着しつつあったようですが、その発祥については諸説あります。
最も古いものとして、昭和10年に神戸のモロゾフ製菓が、外国人向け英字新聞『ザ・ジャパン・アドバタイザー』で、「あなたのバレンタインにチョコレートを贈りましょう」というコピーで広告を出稿したのが始まりとされています。
▶【モロゾフの参考記事】日本のバレンタインはモロゾフからはじまりました。
企業が主導した日本のバレンタイン
モロゾフ以外にも、
・昭和33年:メリーチョコレートが伊勢丹で開催したバレンタインフェア
・昭和35年:森永製菓の新聞広告
・昭和43円:ソニープラザによるプロモーション
などいくつもの企業がバレンタインの普及に関わっています。
菓子メーカーの販促プロモーションの一つとしてスタートしたものが、約50年間に渡り日本の大きなシーズンイベントとして成長し定着し続けてきたのです。